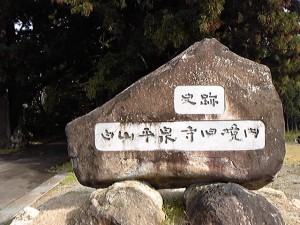最近まったく断熱材がない・・・
お客様の問い合わせは毎日・・・
どう保証してくれんるんだなんていわれる始末・・ こっちが言いたいくらいですよまったく
そんな中で 安定した供給を行なっている ウールブレス ”ムラモト”
の社長”金沢の材木屋”さんのブログはこの断熱材について
なかなかためになる内容ですので引用させていただきました
以下ムラモトさんの内容です・・・ 参考まで
住宅に良く使われる断熱材『グラスウール』『ロックウール』のうち、ロックウール断熱材製造最大手の日東紡が、昨年生産を中止しました。
ロックウール断熱材のおよそ7割ものシェアを誇るガリバー企業でした。
生産を中止した理由は、おそらく資材の高騰と製造コスト・物流コスト増大などのコストを、売価に反映できなかったものと思われます。それとロックウール(岩綿)は、アスベスト(石綿)との違いを消費者に正しく認識してもらうことが出来なかったことも理由の一つだと思われます。
それでも市場がロックウールを認知し評価しているのならば、最大の問題点でもある適正価格での販売ができているはずで、このような結果になることはないのだと思います。
つまり、市場が断熱材にロックウールはいらないと判断されたのだと思います。いらないと判断された理由はいくつかあると思うのですが、近年の高断熱高気密化住宅の気密化にとって、ミネラル系(グラスウール・ロックウール)断熱材は施工面での不利がたたったのだと思います。
繊維系ミネラル断熱材は、充填断熱で室内側に防湿シートを施工するという、気密化が一番難しい工法を取らなければならないという不利が、気密住宅を推進しているグループから敬遠され始めてきたのです。
しかし、充填断熱の工法は一番シンプルで理にかなったものなんです。
従来からの伝統工法や在来工法でも充填断熱が採用され続けました。
ではなぜ繊維系充填断熱工法から外壁断熱や発泡系充填断熱工法に変わっていったのでしょうか?
問題は断熱方法じゃなくて、断熱素材が日本の高温多湿の気候風土に合っていなかったということに尽きるのです。
つまり、より断熱効果を高めるために熱抵抗値の高いグラスウールやロックウールに厚みを増やしていった過程において、壁内結露が起こってしまい、その事後策として発泡系や外壁断熱に流れていったのですね。
当初の断熱材の選定に、ミネラル繊維系断熱材ではなく吸放湿性がある断熱材を選定できていれば、日本の住宅に無意味な高気密高断熱などという工法が蔓延することはなかったと思っています。
今も昔も日本の木造住宅は、調湿・透湿があるほうが長持ちもし、風通しを楽しみ、四季の移り変わりを肌で感じる住まい方が出来るので、良いに決まっています。
気密をして、湿気の流れを完全に遮断する「高気密高断熱」の考え方は、理論は合っています。間違いではありません。でもあれは鉄筋コンクリート住宅に向いている工法です。
木造住宅でこの理論で建ててしまうと、最初のうちは気密がしっかり取れているので、結露の問題は出ませんが、20年以上経ったときに気密化工事が最初のクオリティーを保たれているかが問題なのです。
気密によって結露を防止している工法が、気密が取れなくなれば、通常の断熱工法以上に激しく結露する危険があります。木造住宅の耐久性は、使用する木材が腐朽に強いかどうかの樹種の選定と、木材を腐朽させる菌の繁殖をどう止めるかにあります。
繰り返しますが、気密による木造住宅の耐久性は、その気密化がどれだけ持つのかに掛かっているのです。
ちなみに気密化をするときにどれくらい注意が必要かということと、長期に亘ってその性能を維持することがどれだけ難しいかを検証してみましょう。
まず、一番大事な気密化工事について。
住宅は職人の手仕事です。気密化工事も手仕事で行われます。つまり、人間が行う仕事の正確さにはばらつきがあることが問題なのです。人それぞれの能力の差で気密性能が変わってしまうことが問題。
工事期の施工不良は、竣工時に気密測定をする住宅会社の場合はクリアされますが、まだ住む前までの性能が保障されたに他なりません。
住み始めてからの気密はどう変化していくのでしょうか?
気密化は主に、気密シートによるものと現場発泡によるものがあります。
どちらも石油化学系のものです。
気密シートとはポリエチレンという、エチレンが重合した最も単純な構造を持つ高分子であり、耐環境応力亀裂性が低く、長期(20年以上)の使用に耐えられる素材ではないことが分かります。
現場発泡系も、吹付による現場発泡で隙間なく施工できると謳っていますが、発泡したものは必ず縮みます。縮めば隙間が出来て気密が取れなくなってしまいます。
つまり、「気密」という人為的な工法は必ずほころびが出てきてしまい、超長期の使用に耐えられるだけの保障は出来かねるということに尽きるのです。
気密が気密でなくなり結露しだすと、それを止めることは不可能で、後はただただ結露が腐朽菌の活動を増幅させて、住宅の耐久性を著しく損なうことにつながってしまいます。後々の補修・改修に莫大な費用が生じてしまうのです。
此処まで気密のことで大分時間を使ってしまった・・・。
此処からが本題!
まず結論じみたことから・・・。
気密という人為的な工法を取れば、超長期に亘っての断熱効果や結露防止は難しいことが分かったと思うのです。
ではそうじゃない『呼吸(調湿)出来る素材』での断熱だとどうでしょうか?
最大のアピールポイントは、調湿によって結露環境にさせない!ということなのです。
結露する条件は「湿気の移動」と「温度と湿度の相関関係」です。
気密化は「湿気の移動」を止めることによって結露させないとしています。
調湿断熱材は「温度と湿度の相関関係」を利用することで結露させないのです。
内外の温度差とそのときの湿度の相関関係で結露は起こります。
調湿性能の高い断熱材を使うと、その相関関係を結露しにくい環境にその素材の特性として行ってくれるのです。
人為的なことを行わずして、自然界で培われてきた各素材の物性・特性を利用させてもらう考え方なので、その効果は長期に亘って維持されるのです。
調湿出来る特性を持った断熱材は
「羊毛断熱材」
「セルロースファイバー」
「炭化コルク」
「杉皮ボード」
などがあります。
上記の中でも、その調湿性能は色々ありますし、同じ調湿断熱材にも数ブランドずつありますので、しっかりとその特性である「調湿性能」が発揮できるものを選ぶことが大事です。
弊社はその中でも、調湿性能が最も高い特性を持った羊毛を使って『羊毛断熱材ウールブレス・ウールボード』を製造販売しているのです。
羊毛が持っている高い調湿性能によって、たとえ温度と湿度の相関関係において結露が生じるようなことがあっても、すぐに吸湿がはじまり、結露環境を長く維持できなくすることが出来るので、結露が招く腐朽菌の繁殖も極限まで押さえることが出来るのです。
そして、この効果が羊毛の持っている物性・特性のおかげで半永久的に持続できることが、住宅の耐久性において高い効果を期待できるのです。
人為的な工法ではなく、自然が身につけた特性による断熱材がもたらす素晴らしさを理解できると思っています。
住宅に良く使われる断熱材『グラスウール』『ロックウール』のうち、ロックウール断熱材製造最大手の日東紡が、昨年生産を中止しました。
ロックウール断熱材のおよそ7割ものシェアを誇るガリバー企業でした。
生産を中止した理由は、おそらく資材の高騰と製造コスト・物流コスト増大などのコストを、売価に反映できなかったものと思われます。それとロックウール(岩綿)は、アスベスト(石綿)との違いを消費者に正しく認識してもらうことが出来なかったことも理由の一つだと思われます。
それでも市場がロックウールを認知し評価しているのならば、最大の問題点でもある適正価格での販売ができているはずで、このような結果になることはないのだと思います。
つまり、市場が断熱材にロックウールはいらないと判断されたのだと思います。いらないと判断された理由はいくつかあると思うのですが、近年の高断熱高気密化住宅の気密化にとって、ミネラル系(グラスウール・ロックウール)断熱材は施工面での不利がたたったのだと思います。
繊維系ミネラル断熱材は、充填断熱で室内側に防湿シートを施工するという、気密化が一番難しい工法を取らなければならないという不利が、気密住宅を推進しているグループから敬遠され始めてきたのです。
しかし、充填断熱の工法は一番シンプルで理にかなったものなんです。
従来からの伝統工法や在来工法でも充填断熱が採用され続けました。
ではなぜ繊維系充填断熱工法から外壁断熱や発泡系充填断熱工法に変わっていったのでしょうか?
問題は断熱方法じゃなくて、断熱素材が日本の高温多湿の気候風土に合っていなかったということに尽きるのです。
つまり、より断熱効果を高めるために熱抵抗値の高いグラスウールやロックウールに厚みを増やしていった過程において、壁内結露が起こってしまい、その事後策として発泡系や外壁断熱に流れていったのですね。
当初の断熱材の選定に、ミネラル繊維系断熱材ではなく吸放湿性がある断熱材を選定できていれば、日本の住宅に無意味な高気密高断熱などという工法が蔓延することはなかったと思っています。
今も昔も日本の木造住宅は、調湿・透湿があるほうが長持ちもし、風通しを楽しみ、四季の移り変わりを肌で感じる住まい方が出来るので、良いに決まっています。
気密をして、湿気の流れを完全に遮断する「高気密高断熱」の考え方は、理論は合っています。間違いではありません。でもあれは鉄筋コンクリート住宅に向いている工法です。
木造住宅でこの理論で建ててしまうと、最初のうちは気密がしっかり取れているので、結露の問題は出ませんが、20年以上経ったときに気密化工事が最初のクオリティーを保たれているかが問題なのです。
気密によって結露を防止している工法が、気密が取れなくなれば、通常の断熱工法以上に激しく結露する危険があります。木造住宅の耐久性は、使用する木材が腐朽に強いかどうかの樹種の選定と、木材を腐朽させる菌の繁殖をどう止めるかにあります。
繰り返しますが、気密による木造住宅の耐久性は、その気密化がどれだけ持つのかに掛かっているのです。
ちなみに気密化をするときにどれくらい注意が必要かということと、長期に亘ってその性能を維持することがどれだけ難しいかを検証してみましょう。
まず、一番大事な気密化工事について。
住宅は職人の手仕事です。気密化工事も手仕事で行われます。つまり、人間が行う仕事の正確さにはばらつきがあることが問題なのです。人それぞれの能力の差で気密性能が変わってしまうことが問題。
工事期の施工不良は、竣工時に気密測定をする住宅会社の場合はクリアされますが、まだ住む前までの性能が保障されたに他なりません。
住み始めてからの気密はどう変化していくのでしょうか?
気密化は主に、気密シートによるものと現場発泡によるものがあります。
どちらも石油化学系のものです。
気密シートとはポリエチレンという、エチレンが重合した最も単純な構造を持つ高分子であり、耐環境応力亀裂性が低く、長期(20年以上)の使用に耐えられる素材ではないことが分かります。
現場発泡系も、吹付による現場発泡で隙間なく施工できると謳っていますが、発泡したものは必ず縮みます。縮めば隙間が出来て気密が取れなくなってしまいます。
つまり、「気密」という人為的な工法は必ずほころびが出てきてしまい、超長期の使用に耐えられるだけの保障は出来かねるということに尽きるのです。
気密が気密でなくなり結露しだすと、それを止めることは不可能で、後はただただ結露が腐朽菌の活動を増幅させて、住宅の耐久性を著しく損なうことにつながってしまいます。後々の補修・改修に莫大な費用が生じてしまうのです。
此処まで気密のことで大分時間を使ってしまった・・・。
此処からが本題!
まず結論じみたことから・・・。
気密という人為的な工法を取れば、超長期に亘っての断熱効果や結露防止は難しいことが分かったと思うのです。
ではそうじゃない『呼吸(調湿)出来る素材』での断熱だとどうでしょうか?
最大のアピールポイントは、調湿によって結露環境にさせない!ということなのです。
結露する条件は「湿気の移動」と「温度と湿度の相関関係」です。
気密化は「湿気の移動」を止めることによって結露させないとしています。
調湿断熱材は「温度と湿度の相関関係」を利用することで結露させないのです。
内外の温度差とそのときの湿度の相関関係で結露は起こります。
調湿性能の高い断熱材を使うと、その相関関係を結露しにくい環境にその素材の特性として行ってくれるのです。
人為的なことを行わずして、自然界で培われてきた各素材の物性・特性を利用させてもらう考え方なので、その効果は長期に亘って維持されるのです。
調湿出来る特性を持った断熱材は
「羊毛断熱材」
「セルロースファイバー」
「炭化コルク」
「杉皮ボード」
などがあります。
上記の中でも、その調湿性能は色々ありますし、同じ調湿断熱材にも数ブランドずつありますので、しっかりとその特性である「調湿性能」が発揮できるものを選ぶことが大事です。
弊社はその中でも、調湿性能が最も高い特性を持った羊毛を使って『羊毛断熱材ウールブレス・ウールボード』を製造販売しているのです。
羊毛が持っている高い調湿性能によって、たとえ温度と湿度の相関関係において結露が生じるようなことがあっても、すぐに吸湿がはじまり、結露環境を長く維持できなくすることが出来るので、結露が招く腐朽菌の繁殖も極限まで押さえることが出来るのです。
そして、この効果が羊毛の持っている物性・特性のおかげで半永久的に持続できることが、住宅の耐久性において高い効果を期待できるのです。
人為的な工法ではなく、自然が身につけた特性による断熱材がもたらす素晴らしさを理解できると思っています。